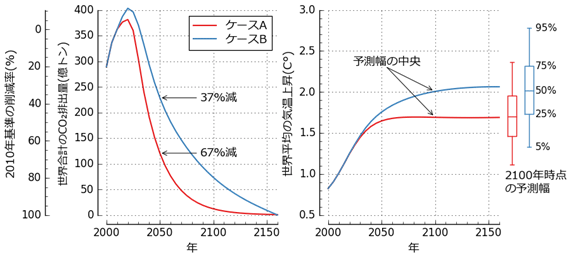この「3℃くらい」というのは、実のところ大きな幅であり、世界中の最新の研究をもってしても、可能性が高いとされる範囲が1.5℃から4.5℃におよぶ。CO2濃度が増加することで地表が暖められる(大気の温室効果が強くなる)ことは良く分かっているが、地球上には、温度の変化を拡大する仕組みがあり、その効果を定量的に評価するのが難しいのである。中でも、温度上昇に伴う雲の変化と、それがさらに温度の変化に影響する仕組みが複雑で、気候感度の不確実性の幅につながっている。気候感度は温度上昇に関する比例定数に相当するので、所定の温度目標(パリ協定では産業革命以前からの温度上昇を2-1.5℃に抑制)の達成に必要な排出削減量は、気候感度に大きく左右されることになる。
具体的な計算例を図に示す。今後150年間の世界全体の排出量を二通り設定し、世界の多数の気候計算モデルのばらつきを考慮して、2100年時点に注目して温度上昇を確率論的に評価した結果である。排出量の少ない方をケースA、多い方をケースBとする。2050年の削減率は、2010年比でそれぞれ67%と37%である。