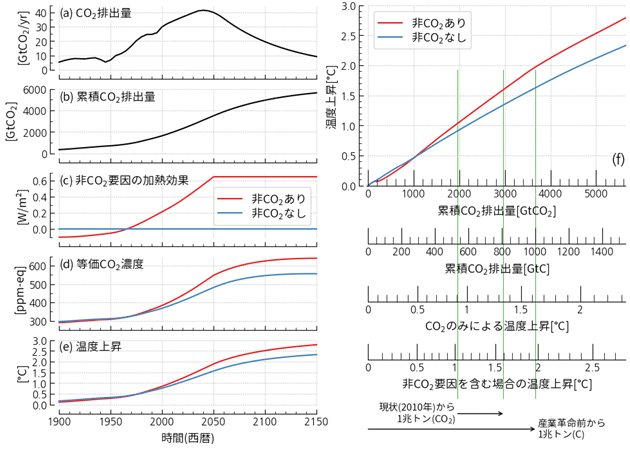排出されたCO2から、大気・海洋・陸域生態系の間のCO2のやりとりを計算すると、大気中のCO2濃度が求まる。非CO2の効果はCO2濃度の増分に対応させることができ、その増分を含めた等価CO2濃度として評価される(図1(d))。この等価CO2濃度に対して、地球の熱の出入りを計算すると、温度上昇が求まる(図1(e))。
計算尺は右下にある4段の目盛の部分で、累積CO2排出量を示す2種類の目盛と、非CO2の効果がない場合とある場合の温度上昇を示す目盛が並んでいる(図1(f))。累積CO2排出量は、今回の気候計算の場合、0を示す左端が1750年で、右端の約5600 GtCO2が2150年に相当する。
二つの温度上昇の目盛は、目的に応じて使い分けることにする。例えば、パリ協定の温度目標(1.5–2 °C)などを念頭に、目標に適合する累積CO2排出量の範囲を調べる場合は、非CO2効果を含む方の目盛を参照する。ただし、将来の非CO2効果の想定には様々な可能性があり、CO2とそれ以外を切り分けて考える必要が出てくる。非CO2効果を含まない方の目盛は、そのような場合に役立つ。
排出量の単位には、第1回の計算尺では、説明の都合でGtC(CO2に含まれる炭素の質量を10億トン単位で表す)を用いた。今回は、世界全体の排出削減の議論で良く使われるGtCO2(CO2としての質量を10億トン単位で表す)を基本とし、GtCを併記する形とした。二つの単位があってややこしいが、1 GtC=3.67 GtCO2の関係から互いに換算できる。
計算尺の最上段にあるGtCO2単位の目盛は、縦軸を温度上昇にとったグラフと共有されている。このグラフで、温度上昇と累積CO2排出量の関係が直線状になることから、冒頭に述べたように、両者が近似的に比例関係にあることを確認できる。計算尺は、実際のところ、このグラフの縦軸の値と横軸の値が対応するように、上下方向に並べたものである。グラフが直線状になることは、計算尺で温度上昇の目盛がほぼ等間隔に並ぶことに対応する。
さて、説明が長くなったが、ここからが1兆トンの話である。
計算尺では、各段の目盛を横断するように上下方向に比べることで、所定の累積CO2排出量に対応する温度上昇を読み取ることができる。図1には、注目点として、現在に当たる時点(ここでは2010年とする)と、二つの1兆トンの箇所に、緑の縦線を引いている。1兆は1000 G(ギガ)のことであるが、二つの1兆トンは起点と単位が異なる。一方は、現在を起点として1000 GtCO2増えたところ、もう一方は、産業革命前(1750年)から1000 GtC増えたところを指す。いずれも、単にきりの良い数値というだけでなく、重要な意味がある。
現在から1000 GtCO2というのは、温度上昇を2 °Cに抑える場合のカーボンバジェットとして、ここ数年で認識されるようになった。環境省で2017年3月にまとめられた長期低炭素ビジョンでも、2050年に向けた大幅削減を描くための前提として、1000 GtCO2のカーボンバジェットに言及されている(注1)。我々の計算尺の場合、現在からの1000 GtCO2に対応する温度上昇(非CO2効果を含む場合)は、1.6 °Cを指している。2 °Cまでには0.4 °Cの余裕があるが、これについては後述する。
もう一つの1兆トン、すなわち産業革命前からの1000 GtCに対応する温度上昇は、CO2のみに起因する温度上昇と累積CO2排出量との間の比例定数に使われ、「累積炭素排出量に対する過渡的気候応答」という名前がついている(注2)。通常は、英語(transient climate response to cumulative carbon emissions)の略称を使って、TCREと表記される。難解な名前だが、要するに、炭素1兆トン(CO2として3.67 兆トン)につき何°C上がるかという指標である。
TCREの値ははっきり分かっているわけではなく、現在のところ、0.8 °Cから2.5 °Cの範囲の可能性が高い(66%超の確率)と評価されている(注3)。我々の計算尺でTCREに相当する温度上昇(定義により、非CO2効果を含めない方の目盛を参照)は1.6 °C強を指しており、0.8 °Cから2.5 °Cの範囲のほぼ真ん中に位置する。つまり、この計算尺から読み取れるカーボンバジェットの情報は、50%確率で所定の温度目標を達成するために残された排出量という意味になる。
このことから、先ほど述べた、現状から1兆トン(CO2として)で1.6 °C(非CO2含む)という結果は、現在の科学的知見に照らして、1.6 °C未満に留まる確率が50%程度と解釈される。この確率は、注目する温度水準を1.7 °C、1.8 °C、…と上げていくと、次第に大きくなる。結局のところ、2 °C目標に適合する1兆トンのカーボンバジェットというのは、不確実性を考慮して、2 °C未満の確率が相当大きくなるよう評価した結果と言える。
それにしても、0.8-2.5 °CというTCREの不確実幅は大きい。この幅次第でカーボンバジェットの数値は大きく変化する。カーボンバジェットを前提に低炭素社会の長期ビジョンを描く基本的な方針は良いとしても、具体的な施策については、不確実幅を低減する努力とその進展に応じた柔軟な見直しが必要だろう。
図1については、今回注目した1兆トンのほかにも、いろいろと考えるべきことがある。次回以降、一つずつ掘り下げてみることにしたい。
(注1)中央環境審議会地球環境部会長期低炭素ビジョン小委員会によるとりまとめ
http://www.env.go.jp/press/103822.html
(注2)炭素部分のみの質量を表すGtCなどの単位は、気候科学の分野で良く使われる。排出されたCO2は、大気・海洋・陸域生態系の間でやりとりされる過程で、様々な無機炭素・有機炭素の形に変化する。このような地球規模の炭素循環の観点では、炭素部分のみの質量に基づく単位が適している。
(注3)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第1作業部会が2013年にとりまとめた第5次評価報告書による
©2017 電力中央研究所