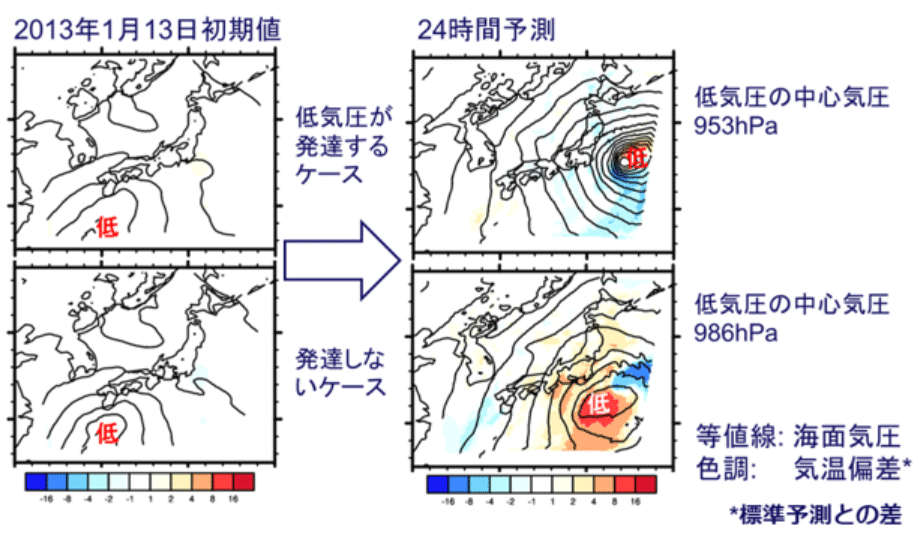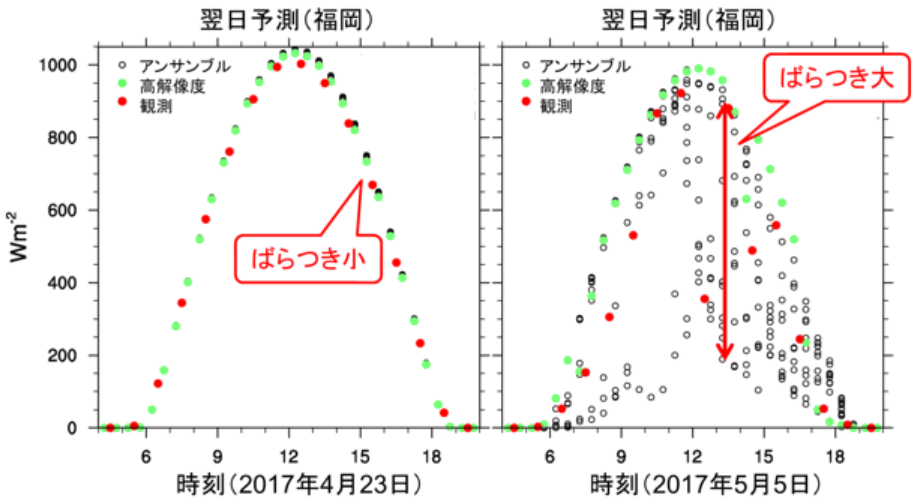気象予測が外れる主な要因として、「数値気象モデルの不完全性」と、「数値気象予測結果はカオス的に振る舞うこと」の2つが挙げられます。
数値気象モデルの不完全性は、計算機資源の制約により、現実大気の変化を厳密に表現できないことに起因するものです。例えば、日射量に影響を及ぼす雲を数値気象モデルで予測する場合、現在の数値気象モデルの空間解像度である2~5 km間隔の計算では非常に粗く、積雲(わた雲)などの比較的規模の小さい雲の再現性に限界があります。また、現在の数値気象モデルでは鉛直方向の層数も100層程度であり、巻雲(すじ雲)などの層状の雲の再現性が悪くなる場合があります。その他にもモデルの不完全性は、雲の生成・消滅や大気中を通過する日射量の減衰・散乱など、大気の状態を表現する様々な物理過程にも見られます。
予測が外れるもう一つの主要因であるカオス的な振る舞いとは、初期値のわずかな違いが、時間の経過とともに指数関数的に成長してしまう現象のことです。このようなカオス的な振る舞いは、台風や低気圧の経路・強度の予測の際によく現れます。
このように、気象予測は外れることがありますが、工夫によって予測精度を向上させることが可能です。数値気象モデル不完全性が原因の場合、モデルの”癖”を統計的な手法を用いて補正することで、ある程度予測を向上させることができます。具体的には、過去の数値気象予測の結果とその予測期間に対応する観測データから両者の統計関係を導き、最新の予測結果に適用することで予測値を補正します。統計関係の作成法としては、回帰、ニューラルネットワーク、カルマンフィルターなど、予測変数の特徴に合わせて、様々な手法が用いられています[1]。
一方、カオス的な振る舞いが原因の場合は、たとえ数値気象予測技術がさらに向上したとしても初期値に誤差が含まれる限り、予測が外れることは避けられません。しかしながら、この認識を逆に応用した技術である「アンサンブル予測手法」が開発されてから、気象予測をうまく活用できるようになりました。アンサンブル予測とは、初期値に摂動(人工的な誤差)を加えた複数の予測のことです。この複数の予測結果にどのくらい違いが生じるかによって、カオス的な振る舞いに起因して予測が外れる程度を知ることができます。アンサンブル予測は1990年頃から実用化され、週間予報や季節予報に利用されています。気象庁では2019年6月から、翌日までを対象とした高解像度のアンサンブル予報情報の提供を開始しました[2]。我々も数日先までの太陽光・風力発電出力予測の信頼性評価を目的に、アンサンブル予測手法を開発しています[3]。
アンサンブル予測の事例を、2013年1月13日から翌1月14日にかけての日本周辺の気象変化を例に紹介します。1月14日は、事前の天気予報では関東地方で雨が予想されていましたが、実際には大雪となった日です。図1は、当時の気圧配置にアンサンブル予測を適用したものです。左側の2つの図は、ともに初期値となる1月13日21時の気圧配置を表しています。2つの天気図とも沖縄付近に低気圧が確認できますが、カオス的振る舞いを考慮した摂動が加えられているため、気圧配置にわずかな差がみられます。右側の図は24時間後の1月14日21時の気圧配置の予測結果です。右上図では低気圧は非常に発達しながら関東の東の海上に抜け、関東地方の気温の低下も予測していますが、右下図では低気圧はそれほど発達せず、経路も本州から南側に離れており、気温の低下も見られません。この結果から、初期値のわずかな差によって、24時間先の予測された天気図が大きく異なったことがわかります。つまり、14日は、低気圧の強度や経路を当てにくく、予測が難しい気象条件であったわけです。